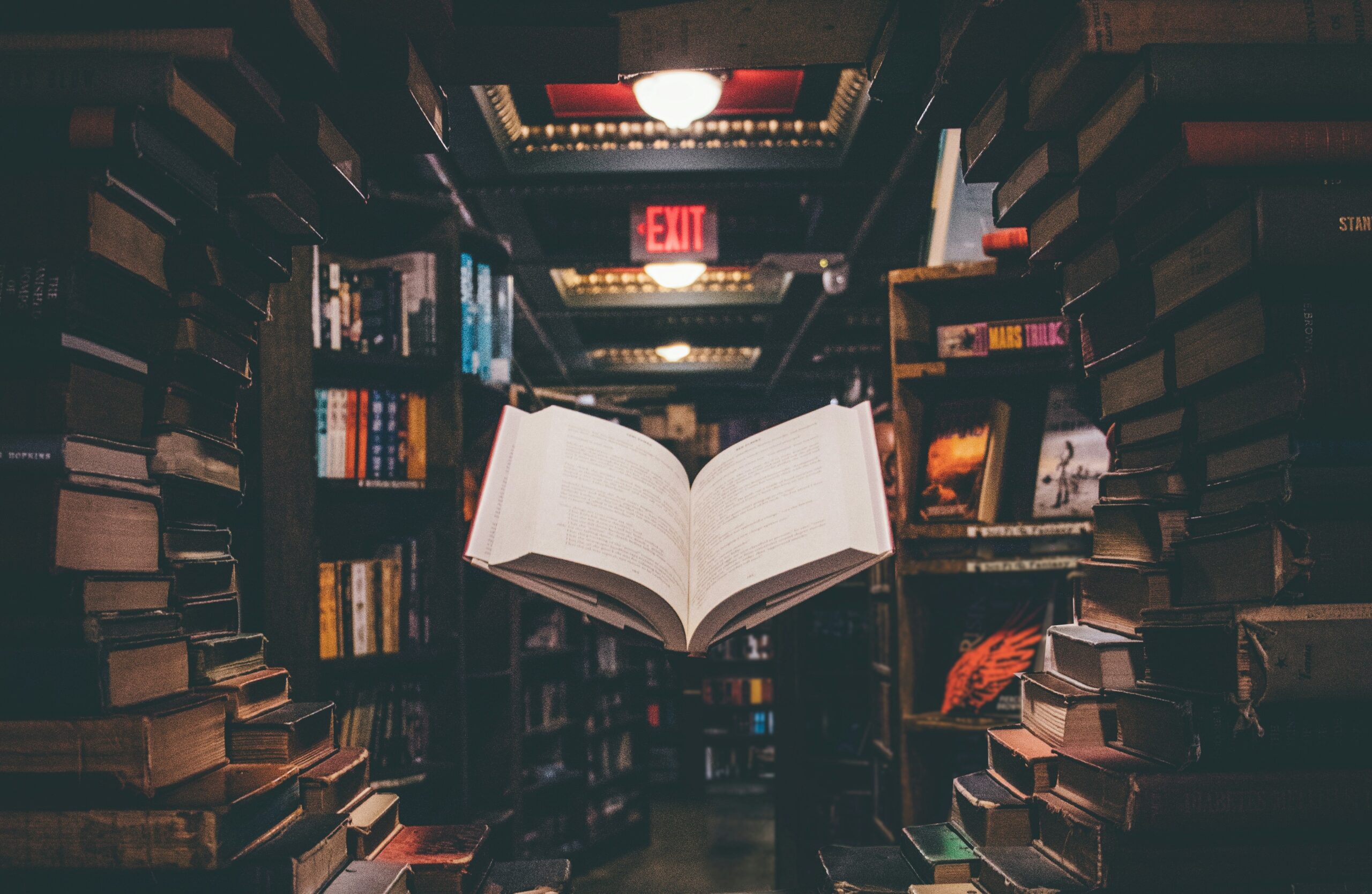宅建試験って「何時間くらい勉強すれば合格できる?」
これは受験を決めたときに真っ先に気になったポイントでした。
ネットで調べると「300時間」「500時間」など目安はありますが、実際には生活スタイルや勉強法で大きく変わります。
私自身、1年目は準備不足で落ち、2年目に勉強計画を見直して合格しました。
この記事では、
- 一般的な宅建試験の必要勉強時間の目安
- 働きながら合格した私の実際の勉強時間
- 1日のスケジュール例
などをまとめます。
「どれくらい勉強すればいい?」と悩む方の参考になれば嬉しいです。
宅建試験って「何時間くらい勉強すれば合格できる?」
「宅建に合格するには何時間くらい勉強すればいいの?」
これは私自身、受験を決めたときに真っ先に気になったポイントでした。
一般的な目安は 300時間〜500時間 と言われています。
しかし実際には「どこまで仕上げるか」「どんな方法をとるか」でかなり変わります。
一般的な目安(300〜500時間)
・短期間集中なら300時間前後でも合格する人も
・じっくり進めるなら500時間くらいかける人も
特に独学の場合は、最初に全体を把握する時間や計画の立て直しなども含めると、500時間近くを見積もっておくと安心です。
人による差が大きい理由
・法律の勉強が初めてかどうか
・過去問を何度も回せるか
・記憶の定着度合い
人それぞれのペースや得意・不得意によって必要時間は大きく変わります。
私自身初めての法律の勉強でした。
聞いたことのない言葉、今まで想像もしなかった土地建物のルールと慣れないものがたくさん出てきたので時間がかかりました。
独学 vs 通学の時間感覚
通学(講座受講):カリキュラム通り進めやすいが、課題をこなす時間も必要
独学:自分のペースで自由だが、計画管理や理解の自走が大事
私の母が随分前に宅建講座通っていましたが、教室の中での学習時間で達成感を簡単に感じてしまって、帰宅後もう一度テキストを開こうとはしていませんでした。
通学スタイルが合うか、独学スタイルが合うかはそれぞれですね。
私が実際にかけた勉強時間
1年目(不合格時)の勉強時間
・総勉強時間:約300時間程度
・平日:2時間くらい
・休日:2〜3時間
6月頃から勉強を始めました。
最初は知らない単語、わからない言い回しを検索して、意味書き出してみたり…
似たような名称の法律の名前を書き出して一覧表を作成してみたり…
丁寧にやる割には、理解できないことに疲れてしまい1日2時間程度しかやらずな日々の繰り返しでした。
ゆったりちょっとずつのペースで行っていたので、過去問演習の時間が足りませんでした。試験形式や出題傾向に慣れないまま本番を迎えたのが大きな敗因です。
2年目(合格時)の総時間と配分
・総勉強時間:約400時間
・平日:2〜3時間
・休日:5〜6時間
過去問を最低4周して、ほぼ回答を覚えるまで繰り返しました。
複数の問題集を使い、文章のパターンに慣れることを意識しました。
1日の勉強時間の目安
平日と休日の時間配分
✅ 平日
- 仕事後に2〜3時間確保
- 通勤中はアプリや教材を読む
✅ 休日
- 5〜6時間集中
- 模試を解く日も確保
働きながらのスケジュール例
私の場合は以下のように組みました。
【平日】
- 21:00〜23:30 勉強
- 移動中:テキストや過去問アプリ
【休日】
- 午前:2時間
- 午後:3〜4時間
宅建試験に向けた勉強計画の立て方
いつから始める?
✅ 目安:試験3〜4か月前
・短期決戦なら7〜8月スタートでもOK
・じっくり進めるなら6月頃から
過去問を何周する?
✅ 最低3〜4周
・1周目:内容理解
・2周目:出題パターン把握
・3周目以降:記憶定着・スピード強化
模試のタイミング
✅ 9月以降に模試を解いて本番シミュレーション
・時間配分を身体で覚える
・苦手分野を最後に潰す
まとめ|コツコツ継続が最大のポイント
宅建試験は「続けた人が勝つ」試験だと思います。
範囲も広く、独学だと挫折しそうになることもありますが、
計画を立てて過去問を繰り返すことで必ず力がつきます。
私も1回落ちてしまいましたが、やり方を見直して2年目に合格できました。
ぜひ、自分に合ったペースで無理なく、でも着実に進めていってください。
この記事が少しでも参考になれば嬉しいです。